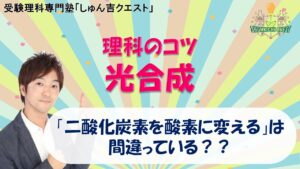【理科のコツ】花のつくり
テーマ:花のつくり・被子植物
花のつくりをイメージで理解する──おしべ・めしべから果実・種子、合弁花・離弁花まで
「おしべ? めしべ? 子ぼう? 胚珠?」──用語だけ並ぶと、花のつくりはとても覚えにくく感じます。
このページでは、動画と図をもとに被子植物の花のつくりを整理し、
果実・種子への変化や合弁花・離弁花まで、入試で狙われるポイントを
まとめとクイズで一気に確認できるようにしました。
花のつくりを含む「生物分野」全体(植物・動物・人体・生態系など)の整理は、生物分野の全体像はこちら。
動画で学ぶ:花のつくり(被子植物)
まずは動画で全体像をつかんでから、このページの図解とまとめで復習していきましょう。
被子植物と花の基本構造
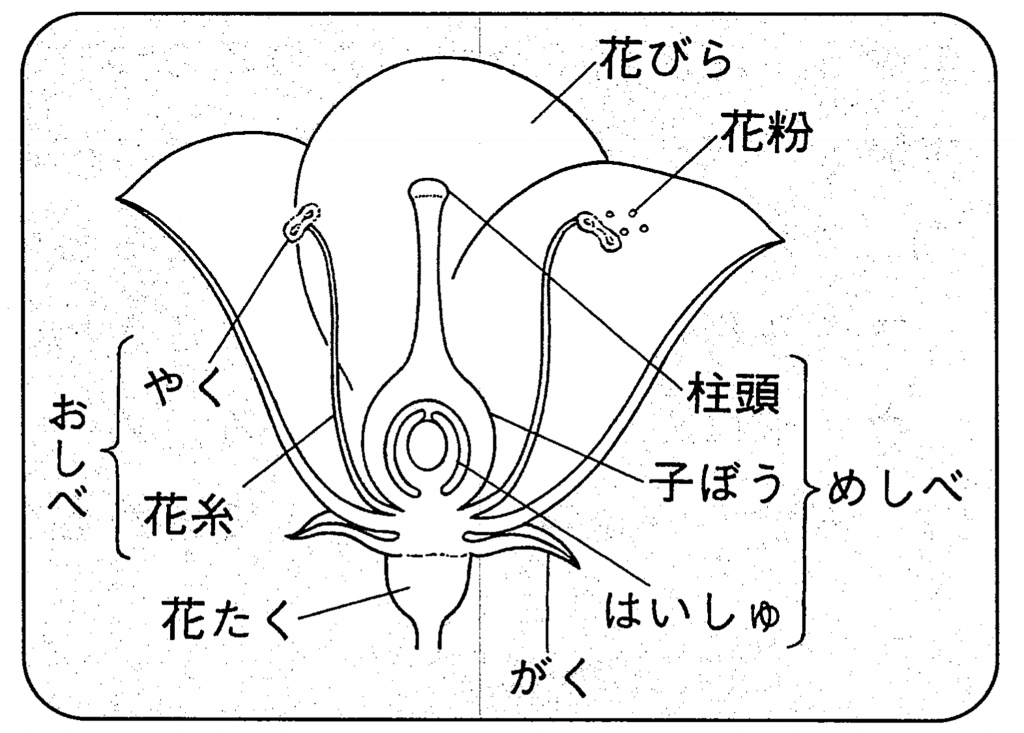
おしべ・めしべ・花びら・がくなど、花のパーツがどう並んでいるかを立体的にイメージしよう。
私たちがふだん「花」と呼んでいるものの多くは、被子植物です。
被子植物は、胚珠が子ぼうに包まれている植物のグループで、
松・イチョウ・ソテツなどの裸子植物と対比されます。
被子植物の花には、次のような共通したパーツがあります。
花の各部の名前と役割
| 部位 | 位置・見た目 | 役割・ポイント |
|---|---|---|
| おしべ | めしべのまわりに並ぶ細い棒状の部分 | 先端のやくの中に花粉が入っている。 花粉症の原因になるのもこの花粉。 棒の部分は花糸と呼ばれるが、入試ではやく+おしべを中心に覚えればOK。 |
| めしべ | 花のど真ん中にドンとある太い部分 | 上の部分が柱頭、下が子ぼう。子ぼうの中に胚珠がある。 受粉後、子ぼう → 果実/胚珠 → 種子になるので、入試頻出。 |
| 花びら (花弁) |
色とりどりで目立つ部分 | 虫や動物を引き寄せる「広告塔」。 テキストでは花弁(かべん)と書かれていることも多いので同じ意味として覚える。 |
| がく (がく片) |
花びらの外側で花を支える緑色っぽい部分 | つぼみのときに花びらを包んで守る役割。 「がく片」と書かれることもあるので、こちらの語もチェック。 |
| 花たく | 花びらやがくのつけ根・土台にあたる部分 | 入試頻度は高くないが、リンゴの「食べている部分」は花たくが肥大化したものという話で登場。 このような果実は偽果と呼ばれる。 |
おしべ・めしべは「オス・メス」とイメージしがちですが、動物のオス・メスとは仕組みが少し違うことも頭の片隅に置いておきましょう。
おしべ・めしべと受粉──果実・種子になるまで
花のつくりで一番重要なのは、受粉→受精→果実・種子という流れです。
ここをセットで覚えると、問題文を読むときに迷いにくくなります。
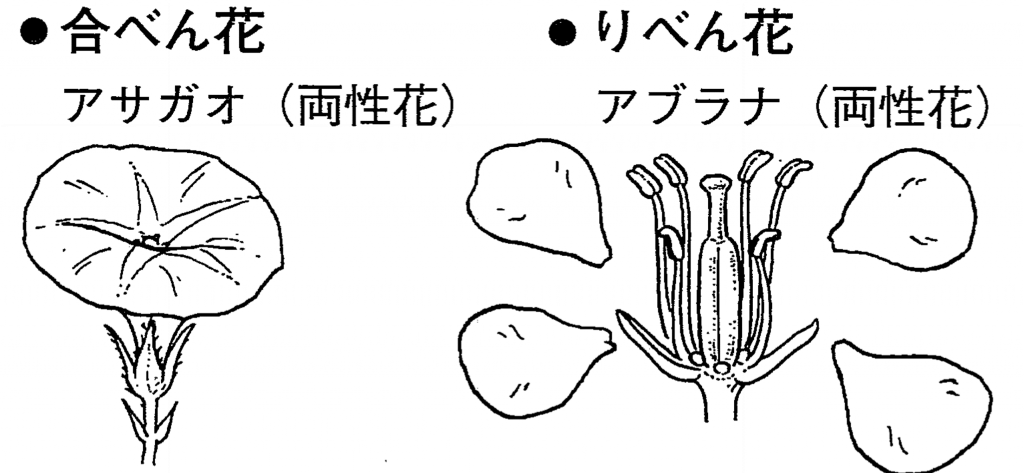
図で「どの部分がのちの果実・種子になるか」を確認しよう。
受粉から果実・種子への流れ
- おしべのやくで作られた花粉が、めしべの柱頭につく(受粉)。
- 花粉の中の細胞がめしべの中を通って胚珠へ向かい、受精が起こる。
- 受精後、子ぼうがふくらんで果実になり、胚珠は種子になる。
したがって、入試では次の対応をしっかりおさえることが大事です。
- 子ぼう → 果実
- 胚珠 → 種子
リンゴは「偽果」の代表例
リンゴの場合、一般に「果実」として食べている部分は、子ぼうそのものではなく花たくがふくらんだ部分です。
このような果実を偽果と呼び、入試でエピソード的に出てくることもあります。
合弁花と離弁花&花占いの豆知識
花びらの付き方にも注目すると、合弁花と離弁花という分類が出てきます。
| 分類 | 特徴 | 具体例 |
|---|---|---|
| 合弁花 | 花びらどうしがくっついて一体化している。 | アサガオ、キク科の仲間(タンポポ・キク など 多数の小さな花が集まった頭状花序)。 |
| 離弁花 | 花びらが一枚ずつバラバラになっている。 | サクラ など。 |
花占いと花びらの枚数
「好き・嫌い・好き・嫌い…」と花びらをちぎる花占いは、
奇数枚の花びらの花(例:サクラの5枚)が楽しくちぎりやすい、といった話も紹介されました。
また、キクやタンポポのようなキク科の植物は、見た目は花びらがたくさんあるように見えますが、
実際にはたくさんの小さな花が集まった構造になっており、合弁花のグループに含まれます。
こうした「日常とつながる豆知識」を知っておくと、植物の単元もぐっと身近に感じられます。
花のつくりについてのまとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 花の基本構造 | ・おしべ:花粉を含む「やく」がある ・めしべ:胚珠を含む「子ぼう」がある ・花びら:花弁と呼ばれることもある ・がく:花を支える部分、がく片とも呼ばれる |
| おしべとめしべの役割 | ・おしべ:花粉を生産し、受粉を担う ・めしべ:受粉後に子ぼうが果実となり、胚珠が種子になる |
| 合弁花と離弁花 | ・合弁花:花びらが一体化している(例:アサガオ、キク科の多く) ・離弁花:花びらが独立している(例:サクラ) |
| 果実化のプロセス | ・子ぼうが肥大化して果実となる ・胚珠が種子となる ・例:リンゴは花たくの部分が肥大化した偽果 |
| 花占いの豆知識 | ・奇数枚の花びらの花(例:サクラ)が花占いに適している ・キクやタンポポはキク科の特殊な例で、多数の小花が集まった合弁花の仲間 |
「どの部分が、のちに何になるのか」を図とセットで覚えると、文章題や記述問題にも強くなります。
理解度チェッククイズ(10問)
最後に、花のつくりと用語がしっかり頭に入っているか、クイズで確認してみましょう。
各問題の「正解を見る」ボタンをクリックすると解答が表示されます。
| 問題 | 選択肢 | 正解を見る |
|---|---|---|
| 1. おしべに含まれる部分はどれですか? | A. 胚珠 B. 子ぼう C. やく D. 柱頭 |
|
| 2. 受粉後に果実になる部分は? | A. 胚珠 B. 子ぼう C. やく D. 花びら |
|
| 3. 花びらが一体化している花の分類は? | A. 離弁花 B. 合弁花 C. 偽果花 D. 花占い花 |
|
| 4. 胚珠が種子になる過程で何が起きますか? | A. 胚珠が花びらに変わる B. 胚珠が種子になる C. 胚珠がやくに変わる D. 胚珠が葉に変わる |
|
| 5. リンゴの果実化について正しい説明は? | A. 子ぼうが直接果実になる B. 花たくが肥大化した偽果 C. やくが果実になる D. 胚珠が果実になる |
|
| 6. 花びらの別名は? | A. 花弁 B. がく片 C. 花たく D. やく |
|
| 7. 合弁花の例として適切なのは? | A. 桜 B. 朝顔 C. タンポポ D. 松 |
|
| 8. 被子植物の特徴は? | A. 子ぼうが裸出している B. 胚珠が子ぼうに包まれている C. 子ぼうが花びらに変化する D. 胚珠が葉に変化する |
|
| 9. 花占いに適しているのは? | A. 偶数枚の花びらの花 B. 奇数枚の花びらの花 C. 離弁花だけ D. 合弁花だけ |
|
| 10. 胚珠が花びらに変わる植物の例は? | A. タンポポ B. 松 C. 桜 D. 該当なし |
まとめ──「どの部分が何になるか」が分かれば怖くない
- 被子植物では、胚珠が子ぼうに包まれているという大きな特徴がある。
- 子ぼう → 果実、胚珠 → 種子という対応は、入試頻出なので必ず押さえる。
- おしべは花粉を作る「やく」、めしべは受粉と果実・種子づくりの中心となる。
- 合弁花・離弁花の違いは花びらの付き方の違いとして図とセットで覚える。
- リンゴの偽果や花占いなど、日常の例と結びつけると記憶に残りやすい。
図を描いたり、実際の花を観察したりしながら、「ここが子ぼうで、ここがのちの種になるんだな」と指でたどってみると、
単なる暗記からイメージで理解する学習に変わっていきます。
花のつくりを含む生物分野の整理は、生物分野の全体像はこちら。
花のつくりを図+言葉でセットにして、入試本番でも迷わないようにしよう
花のつくりは、「どの部分がどう変化して、何になるのか」を整理してしまえば、
語句問題・記述問題・作図問題まで一気に得点源にできる単元です。
動画→図解→まとめ→クイズの順に復習して、知識をしっかり定着させていきましょう。
- 自分で花の断面図を描き、「子ぼう」「胚珠」「やく」「柱頭」などにラベルを付ける。
- 果実と種子の問題では、必ず「もとになった部分」を対応表で整理してみる。
- 身の回りの花(サクラ・アサガオ・キクなど)を観察し、合弁花・離弁花の違いを探してみる。