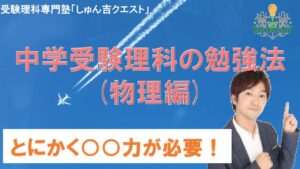地学分野の特徴と引っ掛かりポイント【動画解説】
天体・地震・地層の「つまずき」対策
中学受験理科「地学分野」の特徴とつまずきポイント──図とことばで克服する学習法
「天体の動きがイメージできない」「地震・地層の問題文が読みにくい」──そんな声が多い地学分野。
一方で、パターンをつかめば一気に得点源にもなりうる、非常にコスパの良い分野でもあります。
本記事では、知識50%×計算50%のバランスを持つ地学の特徴と、
生徒がよく引っかかるポイント、その克服方法を、家庭学習でも実践しやすいステップ付きで詳しく解説します。
動画とあわせて読むことで、地学に苦手意識があるお子さまでも「何から手をつければ良いか」がはっきり見えてくるはずです。
※動画では、地学分野のつまずきやすいポイントと指導上の工夫について、講師が詳しく解説しています。
記事とあわせて活用することで、理解が一段と深まります。
地学分野は単元ごとに「図の読み方」「計算の型」が決まっています。まずは気になる単元からピンポイントで確認してください:月の満ち欠け・日食・月食/太陽と1日の動き。
地学分野の全体像と特徴
知識分野と計算分野が「50%ずつ」のバランス
地学分野は、他の分野と比べても知識問題と計算問題のバランスがはっきりしています。
用語暗記だけで乗り切ることも、計算力だけで押し切ることもできず、両方をバランス良く鍛える必要があるのが大きな特徴です。
高野:
知識分野と計算分野が50%ずつなのでバランス良く学習することがポイントになります。
ここで意識したいのは、「知識用の勉強」と「計算用の勉強」を分けて考えることです。
- 知識:用語・現象・しくみを図や写真とセットで覚える
- 計算:公式の暗記だけでなく、「なぜその式になるか」を簡単でもよいので説明できるようにする
たとえば「地震の初期微動継続時間」や「天体の自転・公転に関する周期計算」など、
一見「ややこしい計算」に見える問題も、現象のイメージ+決まった計算パターンに分解すると理解しやすくなります。
まずはどの単元が「知識寄り」「計算寄り」なのかをざっくり把握し、学習時間の配分から見直していきましょう。
「3Dを2Dで考える」天体分野の難しさ
地学の中でも特に多くの生徒が苦手意識を持つのが天体分野です。
実際に空を見上げても分かりづらく、しかも入試問題では平面の図やグラフに置き換えられて出題されるため、
「頭の中でイメージする力」がどうしても必要になります。
高野:天体とかだと3Dになるので、それを
平面に書かれると想像できない人が多いです。これは塾としての課題でもあるんですけど、
ホログラム作って教えたい位です(笑)
ここでつまずく理由はシンプルで、
- 頭の中のイメージ(3D)
- テキストや問題の図(2D)
この2つをつなぐ「翻訳作業」が十分に練習できていないからです。
逆に言えば、この「3D⇔2Dの行き来」をトレーニングしてしまえば、天体分野は一気に得点しやすくなります。
そのため、以下のようなツールを活用して、
天体が空間的に動いているイメージをつかむことが大切です。
- 地球儀を使って、地球の自転・公転や太陽との位置関係を確認する
- 天体シミュレーションアプリなどで、時間とともに動く星や太陽・月の位置を視覚的に見る
- 自分のノートで、「上が北」「右が東」など方位を固定して図を書く
特に家庭学習では、問題を解く前に「まずは図だけをじっくり眺めて、何を表しているのかを言葉で説明する」時間をとるのがおすすめです。
こうした一手間が、後々の速さ・正確さの土台になっていきます。
天体は「1日の動き」と「1年の動き」を分けて整理すると、混乱が激減します:太陽と1日の動き(自転)/太陽と1年の動きと南中高度(公転)/星の動き。
| 地学の要素 | 特徴 | 学習のポイント |
|---|---|---|
| 知識分野 | 用語・現象・しくみの理解が中心。暗記だけでなく、イメージと結びつけることが重要。 |
|
| 計算分野 | 天体の周期計算や地震の到達時刻、グラフ読解など。 |
|
| 天体 | 3Dの動きを2Dの図で表現するためイメージしづらい。方位や「見る人の立場」に注意が必要。 |
|
- 知識×計算の両輪を意識して勉強する
- 図・表・グラフを自分で描き直して整理する
- 条件文の読解と「ワード化」を習慣にする
この3つを意識するだけでも、模試や過去問での「ケアレスミス」が大きく減り、
地学全体の得点が安定してきます。
- 地球儀や天体アプリで立体的なイメージをつくる
- 単位換算だけを集中的に練習する時間を作る
- 間違えた問題は、「どの条件を読み飛ばしたか」まで振り返る
特に、「正解した問題の中にも危なかった箇所がないか」をチェックすることが、
本当の意味での実力アップにつながります。
「どこでつまずいているのか」を一緒に整理したい方へ
当塾「しゅん吉クエスト」では、地学分野を含む理科全体について、一人ひとりの弱点に合わせた個別指導を行っています。
「天体だけが極端に苦手」「計算になると手が止まる」「用語は覚えているのに問題になると解けない」など、
同じ“苦手”でも原因はお子さまによって様々です。
授業では、問題演習だけでなく、
- どの単元で、どのタイプの問題につまずいているのかの分析
- 家庭学習の進め方や復習タイミングといった学習プランの設計
- 模試・過去問の結果を踏まえた「次にやるべきこと」の具体的な提案
「理科に時間はかけているのに成績が安定しない」という場合は、
まずつまずきの原因を一緒に言語化することから始めてみませんか。
講座のラインナップや指導スタイルは、上記「講座案内ページ」からご覧いただけます。
地学分野でよくある「引っ掛かりポイント」
1. 単位系でのミスが多い
高野:地学分野も計算が多いので、やっぱり
単位系で引っ掛かるのが大きいです。
地震のP波・S波の問題や、天体の周期・時刻計算などでは、
「kmとm」「分と秒」といった単位換算でつまずくケースが目立ちます。
正しい式を立てているのに答えだけ合わない……というときは、単位の見落としが原因になっていることが非常に多いです。
単位ミスを減らすには、次のような習慣づけが有効です。
- 計算を始める前に、すべて同じ単位にそろえる(例:km→m、分→秒)
- 問題文に出てくる数値の横に、「m」「km」「分」「秒」など単位を必ず書き添える
- 途中式を省略せず、「×60」「÷1000」などの換算を見える形で書く
- 答えを書いたあとに、「この単位で現実的か?」を一瞬で良いのでチェックする
特に模試・過去問の復習では、「なぜ間違えたか?」を
「知識不足/計算ミス/単位ミス/読み落とし」などに分類しておくと、
自分の弱点がはっきり見えてきます。地学分野はこの「単位ミス」ゾーンを減らすだけでも、
得点が安定しやすくなります。
地震の計算(初期微動継続時間など)の型を固めたい場合は、地震の基礎(P波・S波・到達時刻の整理)もあわせて確認してください。
2. 地震・地層問題で必要になる「国語力」
高野:地震や地層系の問題になると、ある程度用語も知らなきゃいけないのと、
問題にも条件が沢山付加されるので国語力は必要になりますが、
その問題の条件を読解していくっていう所で引っかかる子が多いかなと思います。
地震・地層の問題文は、
- 「図1のA地点で…」「ただし、○○とする」など条件が多い
- 図と本文を行き来しながら読む必要がある
- 「ア〜エのうち、正しいものをすべて選べ」など選択肢も長くなりがち
そのため、理科であっても読解力=国語力が不可欠です。
「知識はあるのに、問題になると正解できない」という場合は、文章の読み方から見直してみましょう。
実際の解き方としては、次のような流れがおすすめです。
- 問題文を一度読み、条件や数字に下線を引く
- 図の中にも「A」「B」「高さ10m」など条件を書き込み、1枚の図で整理する
- 「結局、何を聞かれているのか?」を自分の言葉で短く言い直す
- そのうえで、必要な公式や知識を思い出し、計算・判断に入る
このように①読む → ②図にまとめる → ③聞かれていることを整理 → ④解くという手順を意識することで、
「なんとなく読み流してしまう」状態から抜け出すことができます。特に地学分野では、
このプロセスを丁寧に踏めるかどうかが得点差になります。
条件整理の練習には、設問が長くなりやすい地層の基礎(読み取り・書き込みのコツ)も相性が良いです。
3. 出題側の「ちょっとした工夫」による引っかけ
高野:例えば地層の穴埋めの問題も、ちょっと坂道にするだけで
大分想像しにくくさせることもできます。
天気や風の向きは北半球と南半球で動きが違うので、もう
南半球にするだけでガンガン引っかかってくれます(笑)
地学は、問題作成者が「ひとひねり」しやすい分野でもあります。
基本パターンはシンプルなのに、少しだけ条件を変えることで難易度が一気に上がる、というタイプの問題が多く出題されます。
代表的な「ひとひねり」の例としては、次のようなものがあります。
- 水平な地層を少し傾ける(坂道にする)だけで上下関係が分かりにくくなる
- いつもと同じ風向きの問題を、南半球に変えるだけで動きが逆になる
- 「午前9時」と書かれている問題を、「午前9時から3時間後」と時間をずらして考えさせる
こうした「パターン違い」に対応するには、図を自分で描き直すことが有効です。
設問を読みながら、
- 地層の上下関係を、縦方向の矢印やメモで整理し直す
- 風向きや気圧配置を、北半球と南半球でそれぞれ描いて比べる
- 「変更された条件」(南半球・坂道・時刻のずれなど)に印を付けて、そこから影響をたどる
はじめは時間がかかりますが、同じパターンを3〜4題こなすころには「見え方」が変わってきます。
その感覚をつかめると、入試本番でも「これはあのパターンの少しひねった問題だな」と冷静に対応できるようになります。
「南半球にするだけで逆になる」などの引っかけを整理したいときは、季節と天気(風・気圧・天気の典型パターン)が役立ちます。
図とことばで理解を深める学習法
図や表で「現象のイメージ」をつかむ
高野:(対策としては)図を使うということがすごく大事かなとは思います。
図や表を使って「こういうふうに現象が起こってるんだ」っていうのをまず把握します。
地学分野に限らず、理科では「図や表に情報が集約されている」ことが多くあります。
しかし、図の意味が分からないまま本文だけを読んでも、なかなか頭に入ってきません。
そこでおすすめなのが、次のような「図から読む」学習法です。
- まず図や表だけを見て、何を表しているかを1〜2行で説明してみる
- その説明をもとに、教科書やテキストの本文を読む
- 本文の中で、「さっき自分が言った説明と同じ内容の部分」に線を引く
こうすると、図と文章が頭の中でリンクしやすくなります。
特に、天気図・地震の伝わり方・断層の模式図などは、図の意味が分かるだけで正答率が大きく上がる単元です。
天気図や観測データの読み取りは、天気の観測(気温・湿度・気圧・風向の読み方)で基本の型を固められます。
図を「ワード化」して記述につなげる
高野:そして、それを「ワード化」していくことが大事です。
結局はテストって記述で書くので、図では何かこんな感じで雲できてたっていうことを分かっていても、
それが言葉でアウトプットできないと点数にならないので、やっぱり図や文章っていうのを
教科書とかテキストを参考に覚えていくっていうことが大事かなと思います。
テストで点になるのは「言葉で説明できたとき」です。
図を見て「なんとなく分かった」で終わらせず、必ず自分の言葉に変換する練習をしましょう。
具体的には、次のようなステップがおすすめです。
- 教科書・テキストの図を見て、声に出して説明してみる
- 説明がスムーズに出てこない箇所は、文章を見ながらフレーズごとにマネして言う
- ノートに、図の横に短い説明文を自分の言葉で書き添える
- 慣れてきたら、入試レベルの記述形式(〜だから〜である)でまとめる練習をする
「自分の言葉で説明する」→「教科書の表現に寄せていく」という二段階のプロセスを踏むことで、
理解の深さと、答案としての表現力を同時に伸ばすことができます。
これは地学に限らず、理科全体・さらには社会や国語の記述にも効いてくる汎用的なトレーニングです。
川のはたらきや地形の説明を「ワード化」して答案にする練習には、流れる水のはたらきや川の様子と川がつくる地形もおすすめです。
次に読む:地学の頻出単元をまとめて確認
地学は「単元ごとの型」を早めにそろえるほど得点が安定します。気になるところから順にチェックしてください:
まとめ──「図」と「ことば」で地学を味方にする
地学分野は、「難しい」「イメージしづらい」という声が多い一方で、
ポイントを押さえれば一気に得点源に変えられる分野でもあります。
特に、中学受験の理科では、基本パターンの理解+少しひねった問題への対応力が合否を左右します。
- 知識50%×計算50%のバランスを意識して学習する
- 天体の3Dイメージは、地球儀やアプリ・自作の図で補う
- 単位換算や条件整理など、「ミスが出やすい型」を重点的に練習する
- 図や表を見て、必ず自分の言葉で説明する(ワード化する)
- 地震・地層問題では、理科の知識と同時に国語力(読解力)も鍛える
これらを意識して学習を進めていけば、「なんとなく苦手だった地学」が「むしろ得意」と言える状態に少しずつ近づいていきます。
重要なのは、一気に完璧を目指すのではなく、1単元ずつ、1パターンずつ着実にクリアしていくことです。
動画や個別指導も活用しながら、お子さまにとっての「分かる」「できる」の成功体験を地学分野で積み重ねていきましょう。
その積み重ねが、理科全体の安定した得点力、そして入試本番での大きな自信につながっていきます。
中学受験理科の「次の一歩」を相談したい方へ
「うちの子に合った理科の勉強法を知りたい」「地学だけピンポイントで強化したい」など、
学習のお悩みやご希望に応じて、カスタマイズした指導プランをご提案します。
フォームからのご相談は24時間受付中です。内容を確認のうえ、講師よりご連絡させていただきます。